図書コレクション ~用知の泉~
自社書籍『用地事務マニュアル』英訳版のご紹介
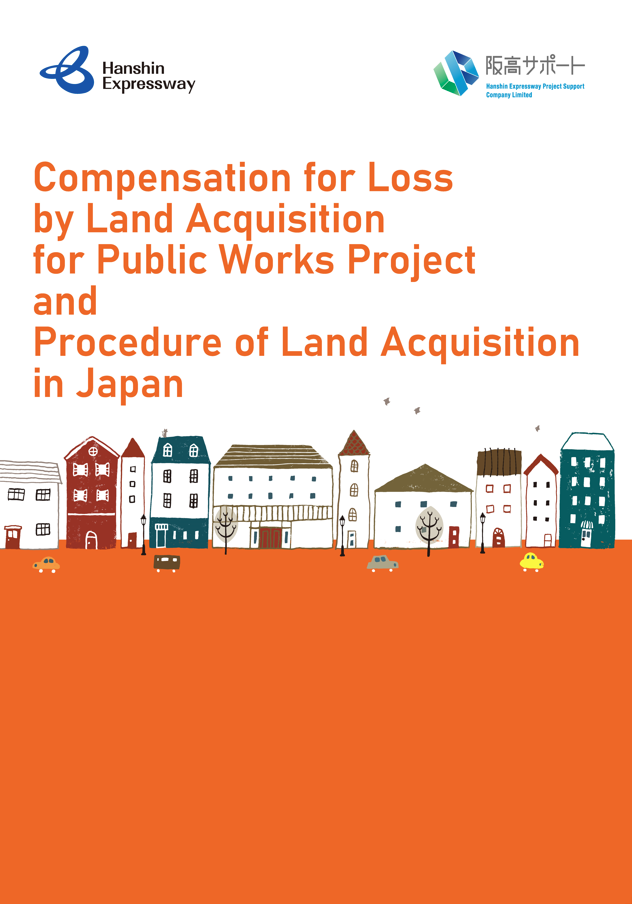
ご紹介の図書
Compensation for Loss by Land Acquisition for Public Works Project and Procedure of Land Acquisition in Japan
公共事業に必要な土地を更地の状態で取得して工事部門に引き渡す。これが用地部門の最終的な仕事です。この用地部門の仕事には、権利調査・測量・物件調査・土地評価・移転補償金算定・補償金照査・用地交渉・契約・補償金支払い・不動産登記・土地管理などの業務があり、それぞれに専門家がいます。
そして、どの部門も重要なのですが、やはり最重要なのは「用地交渉」「補償交渉」ではないかと思います。地権者様との契約があってこその用地取得なのですから。ですが、この「用地交渉」、長年かかって実施しているにもかかわらず、用地事務の説明書では、補償金算定と契約締結の間に一行「用地交渉」と記されるのみの扱いとなっています。これでは、用地初心者の方や交渉担当以外の用地部門の方たちに「用地交渉」「補償交渉」を理解してもらうことはできません。
ところで、1960年代から2000年頃までの用地交渉は、「用地屋」又は「交渉屋」と言われる方たちが一子相伝的に実際の用地交渉の場を通じて、用地交渉技術を若手に伝えていたのです。しかし、最近はこうした「用地屋」さんたちが大量退職した上に、実際の用地交渉の場も減ってしまっています。用地交渉そのものを的確に伝える人達が消えたのに、それに代わる資料や媒体もない、というのが現在の悲しむべき状況です。
そうした思いで、何か「用地交渉」を若者に伝えるのにいいものはないかと探していた時にふと思い出したのです。関西国際空港関連の用地取得に忙殺されたあと、少し時間ができたときに阪神高速道路補償センター(現在は阪神高速地域交流センターに統合)で「補償交渉」を紹介した漫画本を作ったことを(実はビデオも作っています)。
「困ったときに役立つ 用地事務マニュアル テキスト編」を英訳してほしいと阪神高速道路㈱国際室から当時私が所属した阪神高速道路㈱用地センターに依頼があったのは、7年前のことです。当時はコロナ前で阪神高速道路㈱も海外事業に力を入れている時期でもあり、JICAの非自発的住民移転案件でも英訳版があれば国際貢献できるのではないかと安易に考えていた時代でもありました。
最初、国際室からはネイティブによる英訳をいただきましたので、我々はそれをチェックするだけいいので、2年ほどで仕上がるものと考えていました。しかし、その考えは甘かったと言わざるを得ません。そもそも「起業者」がentrepreneurとなっていました。「移転」と言っても、補償基準では、移転、移住、除却等の意味を持っていますので、どう訳し分けるのか。解体撤去も再築工法の取り壊しと復元工法の取り壊しでは方法が異なりますが、これをどう訳し分けるのか。一筆地と一画地をどう訳し分けるのか。調査といっても、surveyもresearchもmeasurementもあります。そもそも、土地と建物が別々の不動産という考えは世界一緒というわけではありません。用地境界は決まっている国もあれば、決まっていない国もあります。登記制度がある国もない国もあります。単純に英訳すれば済むという問題ではなさそうなのが早期にわかりました。
また、英語の構造上、主語・述語・目的語をはっきりしないといけません。日本の規定を改めて読むとほとんど主語がありませんし、分かったようで英語にはできない構造になっています。こうなると、用地の専門用語に精通した者と公共用地取得実務に精通した者がタッグを組んで、英語構造にあった日本語の組み立てから始めないといけないことが分かりました。そこで、慶應義塾大学の松尾教授の助けを借りて、阪神高速道路㈱の用地センターと国際室の用地専門家が毎月1回集まり、議論もしながら、翻訳を初めて丸6年。やっと世に問えるものを完成させることができました。いつの間にか、私は阪神高速道路㈱を卒業し、阪高プロジェクトサポート㈱に移りましたが、この業務はそのまま受け継ぎました。
途中には、専門用語の統一を図る目的で「公共用地の取得に係る損失補償基準要綱」の英訳にも挑戦し、その成果が本書の付録に添付されています。それにしても、損失補償基準要綱の条文の「及び」「並びに」「又は」「若しくは」の重複使用には辟易とさせられました。日本語を読んでいる分にはわかったつもりでいたものが英訳するとなると文節のかかり方が全く読めなくなってしまうのです。たぶん、英訳版の方が分かりやすいと思います。同じことは本文でもいえることで、英語がわかる方はこの英訳版の方が主語、述語がはっきりしていますし、論理的に作られています。日本語版にはあって、英語版にはないのは、「建物等補償の成果品チェック」「補償金に対する課税上の取扱い」「不動産登記手続」となっています。
日本の公共用地取得制度は、世界的に見ると、組織体系と補償規定の細やかさが突出して整備されています。私たちは、この英訳実務書がこれからインフラ整備を進めようとする発展途上国の公務員・実務家の方に非常に役立つものと確信しているところです。ところが、私たちが作業をしている6年間にコロナ禍があり、海外との交流が途切れ、中国が世界第二位のGDP国となり、国際的なサプライチェーンの分断があり、ロシアによる戦争があって国際分断が一層進み、日本の国力低下が顕著になりました。日本のインフラ輸出の声も小さくなり、海外に出ていこうという若者も少なくなりました。
このままでは、この貴重な書籍が活躍する場がないのです。なんとか、この書籍に国際貢献をする場を与えてやってもらいたいのです。興味のある方からの声かけを期待しています。
阪高プロジェクトサポート㈱ 中坪 周作
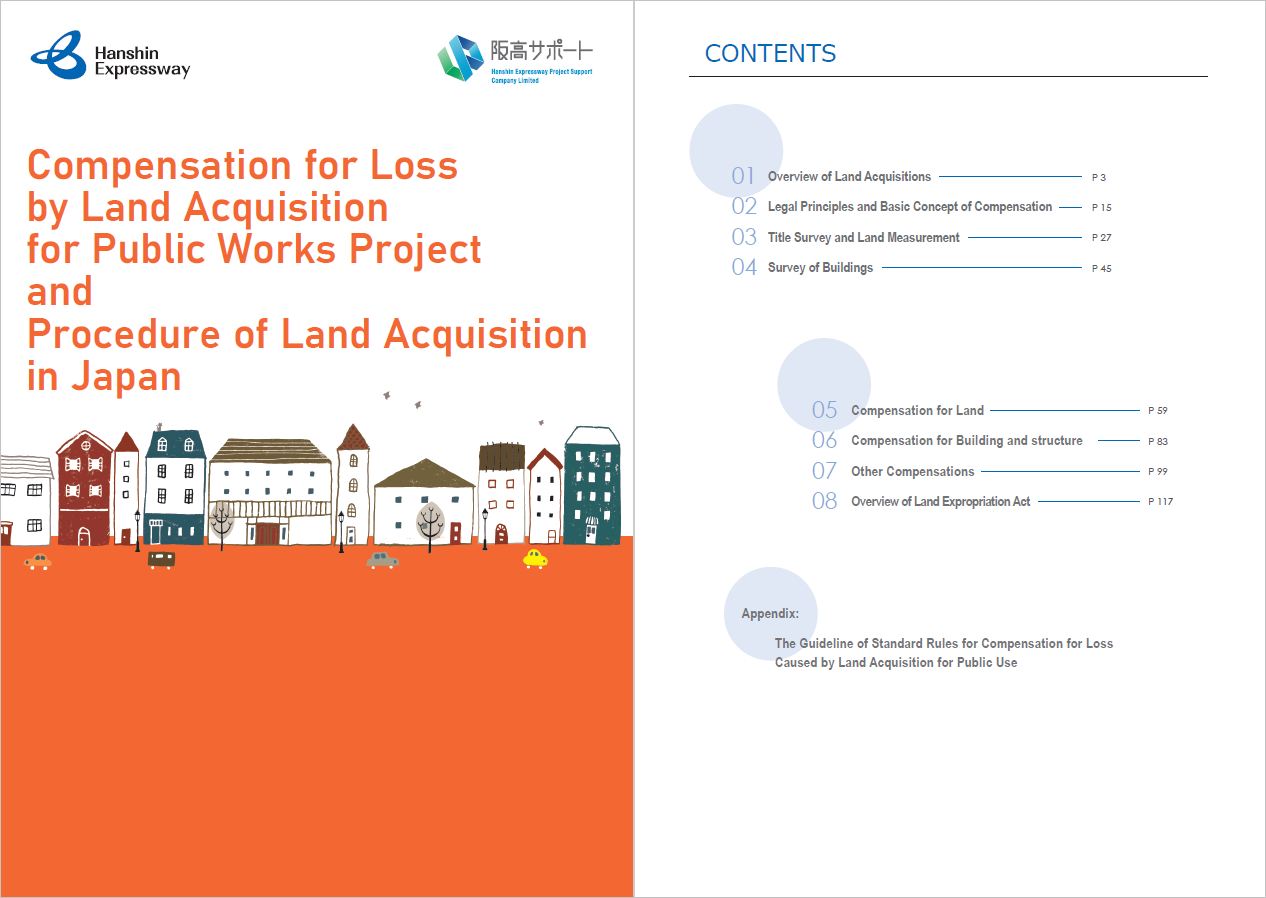
※本書籍は販売はいたしておりません。日本語版はご購入いただけます。
図書コレクション~用知の泉~ バックナンバー
 図書コレクション~用知の泉~ バックナンバーの閲覧は
図書コレクション~用知の泉~ バックナンバーの閲覧は
会員限定です。
会員限定のセミナーへの参加、会員限定の情報の閲覧ができるようになります!
